「額に汗して働く人々の権利を守ること」
それが当事務所のモットーです。
名古屋北法律事務所は、額に汗して働く人々の権利を守ることをモットーにしており、設立当初より、労働事件を事務所の重要な業務と位置付けて取り組んでいます。
個々の労働者の抱える問題に即して、個別の労働事件において、最適な解決を目指すのは当然のことながら、労働者の権利全体を向上させる運動にも積極的に取り組んでいます。また、集団的な労働事件にも労働組合と共に取り組んでいます。
労働事件で弁護士を依頼するメリット
労働事件は、使用者と労働者との紛争ですが、この両者は対等ではありません。使用者には多くの証拠が集中し、それをどのように用いるのかで主導権がありますが、労働者の手元には必ずしも十分な証拠があるとは限りません。使用者の反論は、えてして労働者の人格や能力に対して手加減のない攻撃を加えてくることが多くあります。時間外労働時間であっても、「労働者はその時間遊んでいた、休んでいた」という反論を平気でしてくることもあります。そのような攻撃に耐え、使用者と闘っていくのは非常に大変です。
そのため、労働者が労働事件を闘っていく場合、弁護士のアドバイスを受けられることをおすすめします。弁護士に相談をすることは、法的なアドバイスを受けることができ、「会社から受けた仕打ちが法的に正しいものなのか」を知ることが出来ます。労働事件では労働者を救済するために多数の法律が整備されており、弁護士が法的根拠に基づいた交渉を行うことで労働者の請求が通る可能性が高まることになります。
名古屋北法律事務所に相談するメリット
- 労働事件に多く携わっている弁護士が在籍しているので、様々なアドバイスを受けられます。
- 法的なアドバイスをするだけでなく、依頼者と一緒になって会社と闘う弁護士がいます。
- ケースによっては、労働組合とも連携して、紛争の根本を解決できるような提案をします。
代表的な労働問題
解雇/雇い止めについて
残業代について
労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間までと労働基準法で定められています。この時間を超えて残業をさせる場合には、使用者は残業代(最低1.25倍の割増賃金)を支払わなければならず、これに違反した場合には刑事責任が課せられる場合もあります。また、会社には、労働者の労働時間を適切に把握する義務があります。
しかし、サービス残業を強要され、残業代が払われない事例は、数多くあります。また、使用者が労働時間を管理しておらず、資料が不足している場合もあります。このような場合に、どのように残業代を請求していくのか、どうやって証拠を収集するのかを弁護士がアドバイスします。特に、賃金や残業代は2年という短い時効が定められていますので、早めの相談が良い解決を導きます。
パワハラ、セクハラについて
パワハラは、それが業務上の指導の必要な範囲を超えて、継続的に労働者の人格や尊厳を侵害する場合には違法になる場合があります。
セクハラについても、相当性を越えるような場合には、違法な場合があります。
違法なパワハラやセクハラをされた場合には、加害者だけでなく会社に対しても損害賠償請求することができます。
パワハラ、セクハラの証拠集めから裁判の見込みまで、弁護士が適切な方法をアドバイスいたします。
その他の事例について
その他にも、多くの労働問題があります。男女差別、採用の問題、人事異動の問題、懲戒処分の問題、労働条件に関する問題、派遣労働の問題、社会保険の問題、会社倒産における賃金確保の問題など、取り上げればきりがありません。些細なことでもまずは、お気軽にご相談ください。
更に詳しく解説いたします
内定取り消しに対し、損害の賠償を請求した事例
相談者は、就労開始直前に内定を取り消され、相談に訪れた。当職が事情を確認したところ、内定取り消しの正当性に争う余地があると判断できたため、相手方会社に対し就労の開始とそれまでの損害の賠償の請求を行った。
相手方会社の代理人と複数回協議を重ねた結果、内定の取り消しに同意する代わりに、約5か月分の給与に相当する金銭を解決金として受領した。 弁護士 村上光平
弁護士が依頼者に替わって、退職を代行した事例
相談者は体調不良により退職を検討していたが、自分では言い出すことができなかったため当職へ相談。労働条件通知書上に1か月以上前の申し出や、休職に関する規定が存在しないことなどから会社の対応が懸念されたが、最終的に通知日を基準日として退職の合意をすることができ解決した。 弁護士 村上光平
解雇事件を労働審判手続きで解決
この事件は、機械の開発、製造などを行っている会社に中途採用された労働者が、不当な配転を受けた上、配転後わずかな期間で解雇された事案です。労働審判を申し立てた結果、解雇撤回等の勝利的和解を勝ち取ることができました。
不当解雇の撤回
労働者は、機械の制作に携わり、それまでよりも効率の良い機械を何種類か開発する成果を残しましたが、矯正しても視力が普通の人よりも悪かったのです。入社時にはその説明をしていたのですが、視力が悪いことを理由に、部署の変更と降格を求められ、給料も格段に下がりました。労働者は不本意ながらも解雇されるよりはましと考えて配転に応じ、新たに雇用契約を結び直しました。しかしながら配転のわずか1月半後に、今度は解雇を言い渡されました。
会社側の解雇理由は、労働者が危険な作業を行っていたということですが、この労働者は職場でこれまで事故を起こしたことはなく、言いがかりに等しいものでした。 労働審判では、復職を求めましたが、最終的には解雇撤回の上で、解決金を支払って、会社都合による退職という形で和解をしました。
派遣労働者の解雇事件
2008年9月のリーマンショックを皮切りに、全国で派遣切り(派遣先会社が派遣労働者の受入れを中止すること)が繰り返されました。製造業が盛んな愛知県でも派遣切りが横行をし、事務所弁護士も派遣村等の活動に従事しました。派遣労働者は労働契約を締結する相手と指揮命令をする者が別になっているため、派遣労働者は正社員がやらないようなつらい仕事を命じられたり、景気が悪くなると雇用の調整弁とされ易いという点があります。今回ご紹介をするのは、派遣労働者に対して行われた解雇の事件です。
この派遣労働者は派遣先の研究業務に従事をして、部品の設計などの業務に従事していました。この派遣労働者はいわゆる常用型派遣という、派遣会社に継続的に雇用され、派遣先で業務を継続するという形でした。この労働者は、派遣先の業務を終了し、待機状態に入りましたが、待機期間中、次の派遣先などを十分に探してもらう事が出来ず、また、新たな派遣先に必要な技能の研修などを受けることが出来ず、最終的に派遣先が見つからないと言うことで解雇をされてしまいました。派遣労働者自身には、派遣先に関する情報はありません。また、自分で必要な技能を勉強するのにも限界があります。そのため、派遣会社はどのような派遣先が良いのかを労働者ときちんと協議をすべきです、必要な技能が足りなければ研修などを受けさせるべきなのです。しかしながら、実際には派遣会社にとって、派遣労働者はモノ扱いをされ、そのようなコストを払うことを嫌い、何かしら理由をつけて労働者を解雇することが多くあります。
裁判では、派遣会社が十分な研修、派遣先の探索を行わなかったという点に集中的に立証をしました。会社側は派遣労働者の技能、コミュニケーション能力等が劣っていたという主張をし、労働者に秘密のうちに取得をした派遣先のアンケートなどを提出するなど、なりふり構わない主張をしました。ただ、待機期間中に十分な派遣先探索を行わなかったことは会社側にとって致命的で有り、最終的に、解雇無効を前提とした和解を勝ち取ることが出来ました。この事件は、単なる解雇事件と言うだけで無く、派遣労働者の問題点が非常に良く現れた事件であったと言えます。
三菱電機派遣切り裁判報告
三菱電機名古屋製作所で働いていた派遣労働者が、派遣先である三菱電機に対して派遣切りに対する損害賠償などを求めていた事件で、2013年1月25日、名古屋高等裁判所民事3部(長門栄吉裁判長)は、三菱電機の損害賠償責任を一部認める判決を下しました。
この事件の発端は、2008年末にリーマンショックの影響を理由に、三菱電機名古屋製作所で数百人という大量の派遣切りがなされたことでした。三菱電機では、少なくとも2002年頃から、偽装請負という違法な方法で労働者を受け入れ、労働者派遣法にも大きく違反するほど長期にわたり社外労働者を受け入れていました。本来であれば、長期間労働者を使用するなら、正社員として契約するのが当然ですが、人件費を削減するために違法な派遣労働を続けさせたのです。そして、生産が落ち込めば、真っ先に派遣労働者が契約を切られました。
名古屋北法律事務所を中心に弁護団が組織され、そんな働かせ方はおかしいとして派遣先である三菱電機の責任を追及してきました。派遣労働者は、形式的には派遣元と雇用契約を結びますので、派遣先との契約関係はありません。三菱電機は、裁判で、派遣労働者とは契約関係がないんだから責任もないという主張を展開しました。今回の判決は、三菱電機の主張を退け、「派遣先企業にも、派遣労働者との関係で、その雇用の維持又は安定に対する合理的な期待をいたずらに損なうことがないよう一定の配慮をすべきことが信義則上要請されている」と判断し、原告3名のうち1名に対して三菱電機の不法行為責任を認めました。派遣先にも一定の義務を課したもので重要な判断でした。派遣労働者を、モノのように切り捨ててはいけないという当たり前のことが認められたと考えています。
しかし、控訴審判決は長期にわたって原告らを受け入れてきた三菱電機の使用者としての責任は認めず、損害賠償についても一審で認められた2名について逆転敗訴させた点で、不当な判断でした。もともと労働者派遣法がずさんな法律だったことが、労働者がないがしろにされる最大の要因だと思います。まだ裁判は続きますので、この裁判で原告たちの権利を少しでも実現していきたいと思います。同時に、何でも派遣にして使用者が責任をとらないなんておかしいよねと当たり前にいえる社会をつくり、働く労働者の立場にたった労働者派遣法へと更に抜本的な改正を求めていくことも必要だと感じています。
人材派遣社員の残業代請求
弁護士事務所に持ち込まれる残業代事件は「残業代」は、タイムカードがきちんとそろっているような事件だけでなく、立証に非常な困難を伴う事件も多数取り扱っています。今回は、私が弁護士になって翌年に行った人材派遣会社に勤務する労働者の残業代請求事件です。
人材派遣会社というと、派遣労働者に働かせて、派遣料で楽をしているというイメージだったのですが、その最前線で働く人は過酷な労働環境でした。例えば、急な派遣の依頼に対応するために、深夜まで登録をしている労働者に電話をして探したり、事業所を離れた際も携帯電話を家に持ち帰って対応をしなければならない、朝は朝で朝の弱い派遣労働者に対してモーニングコールをしたりしていました。また、派遣事業所と言っても、一人か二人しか配属されていない所も多く、一人で様々な業務を行わなければばなりませんでした。交渉で解決をすることができず、訴訟を提起することになりましたが、その人材派遣会社は労働時間を全く記録をしていませんでした。
裁判では、労働時間を立証することは原告である労働者の側が証明しなければなりません。そのため、(1)FAX、メールの送信時刻、(2)警備システムの記録時刻、(3)派遣労働者の手配資料等の資料を一つ一つ当たって、個々の労働日の労働時間を立証するようにしました。すべての労働日の労働時間の証拠があったわけではありませんでした。このような作業は弁護士だけでできるものではなかったので、当事者の方にも協力をしていただいて作成をしました。
判決では、立証が難しかったこともあり、請求した金額のすべてを認容されはしませんでした。しかし、証拠資料に乏しい中で労働者の労働時間をどうやって証明していくべきかと言う点で工夫が求められた事件でした。
残業代等請求事件で1000万円以上の解決金で解決した事案
この事件は、運送会社の事案です。依頼者は、入社当初運転手として勤務をしていましたが、その後、課長に昇進し、運行管理等をしていました。課長昇進後は、給料は上がりましたが、いくら残業をしても残業代は支払われなくなりました。当初、依頼者の方は納得をし、時間外勤務を行っていましたが、些細なことで社長とトラブルになり、社長から嫌がらせを受けるようになったことから、労働基準法に従った対応を求めるようになりました。社長は依頼者の態度を不満に思い、たいした理由がないにもかかわらず、運転手に降格をしました。そのため、残業代、降格の無効(裁判提訴後、賞与の請求、解雇による地位確認)等を求めて裁判を起こしました。
裁判では、依頼者が、労働基準法の管理監督者に該当するのかが争点になりました。管理監督者に該当する場合には、残業代の支払いをしなくても良くなります。ただ、実際問題として管理監督者に該当する場合はそうそうありません。この事案でも、人事の決定権は社長にある上、出退勤も自由には決められず、給料も一般の従業員に比べて少しましな程度でした。そのため、基本的に裁判所は管理監督者ではないと言う方向で和解の話を進めることになり、最終的には残業代及び一定の期間分の給与、賞与などを加算をして解決をする事になりました。
残業代の請求は、場合によっては請求金額も高額になることもあります。多くの場合、企業側は管理監督者に該当すると反論をしてきますが、管理監督者に該当する場合はそれ程多くはなく、裁判で企業側の主張を否定する裁判例もたくさんあります。そのため、管理職であると言うだけで残業代の請求を諦めてしまうべきではなく、一度弁護士に相談をすることをお勧めします。
退職に伴う不当請求を阻止した事案
労働事件と聞くと、解雇や未払い賃金の問題が典型的に思い浮かぶかと思いますが、紛争のバリエーションは多岐に及びます。解雇や賃金といった問題は、労働者が、会社に対して請求をすることが多いですが、逆に、労働者が会社から請求を受けるという場合もあります。
事件の内容
依頼者は、比較的小さな製造会社に勤務し、1人で経理を担当していましたが、知人からの誘いもあり、転職を決め、同社を退職することにしました。しかし、依頼者が、退職の予定を伝えると、同社の社長は怒りました。すると、社長は、依頼者の退職に伴って帳簿、通帳、領収書などを確認した結果、不明金が存在しており、これは依頼者が横領したものだと主張し、会社から約50万円の請求をされました。また、その請求と最後の月の給料を相殺すると言って賃金の支払いも拒まれました。もちろん、依頼者は横領などしたことはなく、これは不当な請求だとして争うことにしました。
交渉の結果
まずは、賃金については一方的な相殺は違法だとして支払わせました。肝心な不当請求については、原本は会社が保管していましたが、依頼者も領収書の写しをこまめにファイルに保管していたことも幸いし、これと帳簿や通帳とを照らし合わせる作業をしたうえで会社に対し、不明金についての説明を行うことができました。依頼者が説明が困難な部分ついては、支払に応じて早期に解決して転職先で頑張りたいという意思もあり支払いをすることとはなりましたが、請求された大部分については減額させることができました。
上司のパワハラを訴えて会社が是正をした事案
問題上司に悩まされ・・・
近々に会社を退職するというAさんの労働相談。Aさんは月に数十時間の残業があるものとみなされ、定額の残業手当が支払われてきました。しかし、実際には残業手当が想定する数倍の残業があり、それについて一切残業代が支払われていないというものでした。もっとも、Aさんの相談の本丸は残業代ではなく、辞職の原因となった上司によるパワハラでした。
パワハラの相談はとても多いのですが、指導の範囲を超えて「違法」であると争うにはなかなか難しい事案や、録音等の客観的な証拠がなく、言った・言わないの話になり立証が難しい事案は残念ながら少なくありません。そんな中、Aさんはバッチリと録音を残し、職場に残る同僚の証言への協力もとりつけており、立証に申し分ありませんでした。何よりその上司によるパワハラの内容も人道的・刑事的にかなり問題があるものでした。
会社の意外な対応
そこで、会社に対して正規の残業代とパワハラに対する慰謝料を請求しました。会社は弁護士をつけたものの、ほとんど争わず、こちらの言い分をほぼ認めてきました。
上司によるパワハラは他の同僚にも向けられていたことを心配するAさんの希望もあり、和解書の中に、会社には法律上、労働者に対する安全配慮義務があるので、今後、ハラスメントが生じない職場環境を整えることを誓約するというような一文を入れるように要求したところ、会社はこれも受諾しました。
私は、会社は矛を収めさせるために形だけ受け入れたのではと疑っていたところもありましたが、会社は現に和解締結前から、本社から人を派遣し、上司の実態調査に乗り出していたようです。そして、社員からの聴き取りからも、上司の問題行動が明るみに出たようで、残った社員にも会社として正式に謝罪をしたほか、上司にも厳重な処分が下ったようです。
会社は予め労務問題が起きないよう努めることが一番ですが、社員からの請求をきっかけにでも自浄努力が速やかに・実効的に動くことは望ましく、こういう会社が増えることを期待しています。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税込)
下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。
たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。
解雇無効を争う場合
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 交渉 | 11〜33万円 |
|
| 労働審判 | 22〜44万円 | |
| 訴訟 | 33〜55万円 | |
| 仮処分 | 22〜44万円 |
|
残業代請求事件
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 交渉、労働審判、 訴訟 |
請求金額の5.5〜8.8% (最低11万円) |
経済的利益の11〜17.6% |
労災事件
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 労災申請の代理人 | 22〜44万円 | 労災給付額の11〜17.6% (年金の場合は7年分で計算します。) |
| 証拠保全 | 22〜44万円 ただし、労災申請または会社に対する損害賠償を同時に依頼される場合は減額いたします。 |
発生致しません。 |
| 会社に対しての 損害賠償請求 交渉、訴訟 |
5.5〜8.8% (最低11万円) |
|
解雇無効を労働審判で争う場合
- 勤務していた会社を能力不足を理由に解雇されました。会社に対して解雇の撤回と職場復帰を求める内容証明郵便を送付して交渉をしましたが、会社は解雇を撤回しませんでした。
- 労働審判を申立てたところ、会社の解雇は無効であることを前提としつつ、職場復帰をせずに会社が労働者に500万円の解決金を支払うことで調停をしました。
このケースの弁護士費用
このケースでは、交渉段階で着手金を11万円としました。労働審判段階で着手金を33万円としましたが、交渉段階の着手金11万円を充当したので、追加で22万円の着手金をお支払頂きました。
解決金をもらっての解決だったので、成功報酬は経済的利益500万円の11%+19万8000円、74万8000円となります。
上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え、 3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
| 3,000万円を超え、 3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は11万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。




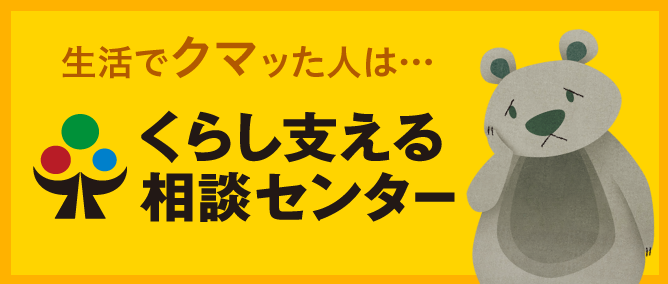



















雇用主といっても、簡単に解雇はできません。「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇は無効となります。また、契約社員など期間の定めがある労働者の場合も、「やむをえない事由」がなければ期間途中に解雇をすることはできません(労働契約法17条)。
もし解雇といわれても、仕方ないとあきらめる必要はありません。解雇が有効かどうか、弁護士が適切なアドバイスをいたします。解雇された場合には、その理由を知るために、会社に対して解雇理由証明書を請求することができます。
解雇が無効であると考えられる場合には、事案に応じて復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めるなど、適切な解決方法をアドバイスいたします。