新たな一歩を踏み出すために
離婚を巡る紛争は、主張の組立て、証拠の分析、手続の選択など、専門的な知識経験が必要とされる分野です。名古屋北法律事務所の弁護士は離婚に関する法律相談、代理人としての豊富な経験を有しており、ご相談者のお力になることができます。法律相談の際に女性の弁護士を選ぶこともできます。
離婚問題で弁護士ができること
離婚の種類には夫婦間で話し合う「協議離婚」、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う「調停離婚」、裁判官の審判により離婚を成立させる「審判離婚」、訴訟にて離婚を争う「裁判離婚」の4種があります。
離婚の手続きは上図のような流れで進みます。弁護士は「当事者による話し合い」の段階からご相談を承ることができます。
離婚をする際には、財産分与・慰謝料・養育費等のお金の問題、親権、面会交流などの子どもの問題など様々な問題が存在します。口約束だけでは後日争いがむし返されることもあり、弁護士にご相談いただくことで、その後の新しい生活をスムーズにスタートさせることができます。また、DVや外国の方との離婚など話し合いが難しい状況であれば、なお弁護士へのご相談をおすすめします。
- 離婚とお金
財産分与、慰謝料、養育費など - 離婚と子ども
親権、面会交流権など - 離婚に関する様々な問題
DV、外国の方との離婚など
裁判で離婚する場合に必要な理由について
上図の流れのように、話し合いで離婚合意が得られない場合、訴訟による離婚手続きをとることになります。ただし、全ての場合で離婚が成立する訳ではありません。裁判で離婚する場合には以下の5つの理由のうち少なくとも1つに該当する必要があります。
民法の定めている5つの法定離婚原因
- 不貞行為があったとき
- 配偶者に悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
最後の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」は表現が抽象的ですが、たとえば配偶者から暴力や暴言を受けている、生活費を渡さない、性格、宗教等の著しい不一致などが代表的です。
別れた元配偶者からの財産分与請求〜在日韓国人離婚の落とし穴〜
離婚ができなかった離婚事件の話
暴力が日常の家庭
Aさんは70歳代の女性。22歳で見合い結婚をして50年ほど。結婚当初から、夫は家庭内では暴君で、すぐにAさんに対して殴る蹴るの暴力をふるいました。夫の仕事が長続きせず十分な収入のない中、Aさんは夫と一緒に働きながら子どもたちを育て上げました。
自由のない生活の辛さ
一番辛かったのは常に行動を監視され制限されたことでした。Aさんは洗濯物を干すために一人でベランダに出ることさえ許されませんでした。夫は、地元に職がなく遠方に出稼ぎに行くことになると、Aさんに同行して同じ工場で働くよう命じました。Aさんは半世紀近くの長い間、この夫から逃げることはできないと諦めていました。
意外な転機と意外な結末
数年前、Aさんは癌が見つかって入院し、そこではじめてAさんは夫婦関係の悩みを病院の職員に話しました。そして他人の共感を得たことで、夫の元から去ることを決意することになったのです。ただ、その後Aさんは離婚の調停を申し立てましたが、高齢の夫が病気に倒れ寝たきりになったため、調停を取り下げ、結局、離婚はできませんでした。
周囲の助けが必要です
自由を知ったAさんはとても明るく、いつも他人への感謝の言葉を口にされていました。自分のために時間をつかう喜びを知りました、私は今はじめて人生を生きています、と言っていただいたことが忘れられません。
典型的なDV(家庭内暴力)家庭でしたから、もしもっと早くAさんが誰かに相談できていたならば、もっと早く自由な生活ができていたでしょう。DVの被害者が勇気を出して踏み出すには周囲の気づきと励ましが必要です。弁護士にももっと気軽に相談にきていただきたいと切に思った事案でした。
別居後の養育費請求の事案
Aさんは、夫の不貞行為が原因で、数年前に調停で離婚し、小学生の男の子を一人で育てているシングルマザーです。離婚後やっと落ち着いてきたと思ったら、元夫からの養育費が遅れがちになり、ついにまったく支払われなくなりました。
最近の傾向として、養育費の請求事件が増えています。養育費は、未成熟な子どもが生活するために必要な費用のことです。離婚して別居しても親子の縁は切れませんから、親である限り子どもの扶養義務として生活費の一部を負担することは当然の責務なのです。かつては養育費の取り決めをして離婚する夫婦は3割程度でした。しかし子どもの貧困、とりわけ母子家庭の経済状況は厳しく、片親だけで子どもの生活を丸抱えするのはたいへんだという事情もあり、離婚後も養育費をもらおうという意識が高まっているようです。養育費の金額は、裁判所で決める場合には、簡単な算定表をもとに決められることが多く、子どもの年齢や双方の収入に応じた負担をすることになっています。
Aさんの場合は、色々な事情を加味して、相当譲歩して養育費を決めました。それでも支払わないなんて許せないというのが、Aさんの言い分です。調停や審判で決まった養育費の不払いは、まずは家庭裁判所の書記官に履行するよう相手に勧告してもらうことができます。それでも支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行をすることにならざるをえません。Aさんの場合は、履行勧告をしたところ、元夫側は、給料が大幅にダウンしたということで、元夫側から家庭裁判所に養育費の減額の調停を申したてることになり、そこで話し合うことになりました。しかし、突然、何の連絡もなく養育費を止められたAさんは話し合いをする気持ちになれません。結局、調停はまとまらず、家庭裁判所の審判で少し減額した養育費が決まりました。
入ってくると思っていた養育費の支払いがないと、それをあてにしていた方は、生活に大きな支障を来してしまいます。万が一、約束した養育費の支払いができなくなったときは、必ず養育費の減額の話し合いの機会をもつようにしていただきたいものです。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税込)
下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。
離婚
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 交渉 | 22万〜33万円 | 着手金と同程度 |
| 調停 | 33万〜44万円 | |
| 訴訟 | 33万〜55万円 |
事案により5回目以降の裁判所への出廷については、日当(2万2000円)を追加でいただく場合があります。
離婚事件と一緒に他の請求をする場合は別途費用がかかりますが、それぞれの請求にかかる着手金・報酬金の合計額から減額いたします。
婚姻費用、養育費
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 調停 | 22万円〜 | 上限7年分×11% |
| 審判 | 22万円〜 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
年金分割
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 調停・審判、交渉(合意) | 8万8000円 | 報酬は発生しません。 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金はいただきません。
面会交流
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 調停 | 22万〜33万円 | 22万〜33万円 |
| 審判 | 22万〜33万円 |
- 離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
- 5回目以降の裁判所への出廷については、日当(2万2000円)を追加でいただく場合があります。
保護命令
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 審判 | 11万円 | 11万円 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
不貞の相手方への慰謝料請求(200万円を請求する場合の例)
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 交渉 | 11万円 | 経済的利益の11〜17.6% |
| 訴訟 | 22万円 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
子の引き渡し請求
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 調停、審判 | 22万円 | 22万円 |
審判前の保全処分の場合は着手金22万円となります。
財産分与等のための保全命令
| 手続 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 審判前の保全処分、 民事保全等 |
22万円 | 本案と一緒に 請求いたします。 |
財産分与その他の財産上の請求
上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え、 3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
| 3,000万円を超え、 3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は11万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。




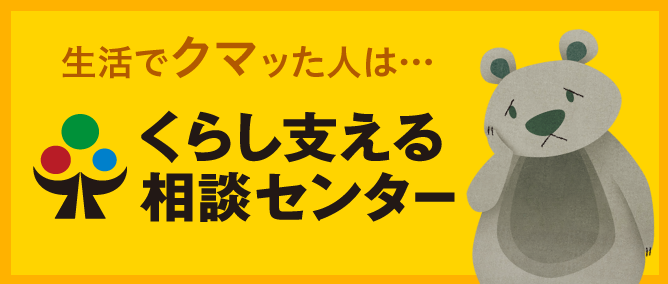



















離婚後5年以上たってから財産分与!?
日本でも韓国でも、財産分与を請求できるのは離婚後2年間とされています。在日韓国人のAさんは、離婚後5年以上が経ってから突然財産分与調停を起こされ、相談に来られました。
韓国で離婚手続きをしないでいたら・・・
ともに在日韓国人のAさん夫妻は、日本の役場に離婚届を提出しただけで別れ、それから5年以上経ってから韓国領事館で離婚手続をしました。夫妻の家族関係登録には、領事館での届出日が離婚日と記載されました。ここに目を付けた元配偶者が、離婚後にAさんが取得した財産を分割すべきだと主張してきたのです。
韓国法の手続きをしないと離婚と認められないけれど・・・?
調停では、Aさん夫妻の離婚日は、日本と韓国のどちらで届出をした日かが争点に。在日韓国人の離婚は韓国法によるものとされており、韓国では、協議離婚でも法院(裁判所)の意思確認が必要で、日本で離婚届を出しただけでは有効な離婚と認められないので問題となったのです。
しかし、実は在日韓国人同士の場合、2004年9月19日までは、韓国大法院戸籍例規第322号で、日本の離婚届を出しただけで韓国法上も有効な離婚と認める取扱いがされていたので、この日よりも前に離婚届を出していたAさんは財産を守ることができました。