正確な知識経験に裏打ちされたアドバイスを行います。
刑事事件は、身近に起こるものではありませんが、いざ自分や家族が逮捕されたり、警察で取り調べを受けた場合、身近に相談できる存在が必要不可欠です。
刑事事件の弁護人となることができるのは弁護士のみであり、弁護士でなければ正確な知識経験に裏打ちされたアドバイスをすることができません。名古屋北法律事務所の弁護士は全員刑事弁護人として毎年一定の刑事事件を受任しており、刑事手続きの流れや見通し、保釈ができるのか、起訴されるかどうか、起訴された場合、有罪になるのか無罪になるのか、執行猶予つきの判決になるのかといった点についてアドバイスをすることができます。
弁護人の具体的な活動について
起訴される前の段階
起訴後の段階
- 起訴後には裁判に向けてどういう証拠を取り調べるかどうかについて主張したり、証人などを尋問したりします。また、証拠を分析して犯罪かどうかを争ったり、情状に酌量すべき事情を主張したりします。
- また、起訴後には保釈によって身柄解放を受けることができるので、被疑者段階よりもより積極的に身柄解放を求めていきます。
- 一定の重大事件では裁判員裁判となり、口頭でのやりとりが重視されたり、争点を絞って短期間で集中的に審理するという点で通常の事件とは異なります。名古屋北法律事務所の弁護士は裁判員裁判に対応できるように研修に積極的に参加するなどし、日々研鑽に努めております。
少年事件
未成年者が犯罪を犯した場合には、少年事件となり、家庭裁判所の少年審判という手続で処分を決めます。少年事件の目的は刑事事件とは異なり、少年の更生を図ることが目的です。
少年審判では弁護人ではなく、付添人といいます。付添人は少年のパートナーとして、少年の犯罪の嫌疑に対して争ったり、犯罪に至った経緯や原因について少年の代弁者となります。
調査官と面談したり、裁判官に対して処分の意見を述べることもでき、付添人の活動や意見が少年審判の結果に大きな影響力を持つ場合もあります。
刑事告訴
犯罪の被害者となった場合に警察などに加害者の刑事処分を求めることができます。弁護士は法律の専門家としてどのような犯罪に該当するか、犯罪を立証するためにはどのような証拠が必要かについての知識があります。普通に被害申告をしても頼んだのではなかなか警察が動かない事件でも、弁護士が事案を整理したり、調査をして告訴をした場合、警察の捜査活動を促しやすいです。
名古屋北法律事務所では、犯罪被害者の方の加害者に対する刑事告訴に関するご相談、ご依頼もお受けいたします。
とある2件の窃盗事件
似ている(?)2つの窃盗事件
国選弁護人としてついたAさんとBさんを紹介します。
Aさんは、スーパーで弁当など数千円分を万引きした件で逮捕されました。Aさんは、過去にも裁判で有罪となったことが2回あり、そのいずれもが窃盗でした。刑務所を出所後、生活保護を受給して生活していた方でした。Bさんは、換金目的で自転車を窃盗した件で逮捕されました。Bさんも過去に何度も裁判で有罪となったことがあり、やはりすべてが窃盗でした。そして、この方も刑務所を出所後、生活保護を受給されていた方でした。
Bさんの案件が私のもとに来たときは、また、Aさんみたいな感じかなと思っていましたが、お話しを聞いているとその2人は随分違ったものでした。
異なる2人の実態
話をきくと、Aさんは、生計困難者の自立を支援するために無料か低額で貸し与えられる簡易住宅である「無料低額宿泊所」に入居している方でした。この施設は社会福祉法に基づく自立支援のための施設なのですが、中には、本来の趣旨から外れて、ビジネスとする業者もいます。Aさんの入居先も11万強ある保護費から、家賃や共益費など様々な名目で天引き、Aさんの手元には2万円が残るだけという状態でした。もっとも、Aさんはやりくり上手で、お金が尽きて窃盗に及んだというわけではなく、少ない手持ちからお金が減るのが嫌で窃盗に及んだというものでした。
他方、Bさんは、ひとり暮らしで、保護費から自由に生計を立てることができたものの、無計画にアイドルのCDなど欲しいものはとにかく購入していていました。ただし、欲しいものを購入してばかりなので月末には無一文になるため、物を盗んで換金して月末の生活費にあてる、そんな生活でした。
弁護活動を経て思うこと
Aさんは、多額のピンハネさえなければ十分に自活できる方で、もし自由に使えるお金が1万でも2万でも多くあったら窃盗はしていなかったとおっしゃっていました。Bさんは、実は刑務所から出所したのちしばらくは生活保護者を支援するNPO法人にお世話になっていたらしく、その期間はNPOの方の金銭管理もあり窃盗に及ぶようなことも無かったとのこと。
窃盗に至る動機や経緯は様々ですが、刑務所での刑期を終わらせれば、再犯はなくなるとは言い切えません。今回のAさん、Bさんもともに窃盗の再犯です。しかし、話を聞いてみると、窃盗に結び付くところを適切にフォローすればまた再犯も回避できるのではと思います。こういった観点は、なかなか弁護士だけでは難しいところであり、出所後の福祉関係のサポートの必要性をひしひしと感じた事件でした。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の事案
先日、「過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪」という罪名の国選弁護事件を担当しました。非常に長い罪名ですが、アルコール等の影響により自動車を運転をし、過失で人を怪我させた場合で、事故後に体内のアルコール等の濃度を減少させる犯罪を言います。
逃げ得を防止する
これは、飲酒運転による交通事故に対して、事故現場から逃走するなどしてアルコールに関する捜査が困難になることを防ぐ、いわゆる「逃げ得」を防止するために、2014年5月20日に施行されました。通常の事故では7年以下の懲役刑ですが、この犯罪は12年以下の懲役なので、同じ事故でも逃げてアルコールの影響を免れようとした方がよりも重い懲役刑を科されるのです。
飲酒運転事故から逃げるということ
私が担当した被告人はまだ20代で、飲酒運転による事故が発覚をすることで、妊娠中の婚約者に心配をかけてはいけないと思い、事故後、現場から逃走をしたそうです。事故後、自動車保険を使えることが判り、被告人を伴って、被害者に謝罪に行くなどしました。被害者が怪我で苦しんでいる様子を見て、被告人には自分のやった行為の重さを認識してもらえたと思います。
今回は、幸いにも被害者の方は一命をとりとめ、被告人の更生の点から執行猶予判決となりましたが、怪我の程度がもっと重かったり、事故現場が人通りの少ない場所であったりすれば、被害者が命を落としていた可能性も十分ありますし、被告人が逮捕されなかった可能性もあります。そういった点から、飲酒運転を免れようと逃走する行為に対しては、ある程度重く処罰をすることは必要ではないかと考えさせられる事件でした。
保釈が認められた事案
保釈とは、刑事事件で保釈金を納めることで一時的に被告人の身柄を解放する制度です。今回は私が弁護人をした事件を題材に、実際の刑事事件でどのように保釈を使っていったのかをお話しします。
Aさんの例
Aさんは兵庫県に居住していた方ですが、愛知県内の共犯と一緒に逮捕監禁罪をしたことで逮捕されました。このような共犯関係の事件では、共犯者間で口裏を合わせることを防ぐために弁護人以外との面会を禁止する決定がされることが多いです。Aさんも同様の決定がされたので、Aさんの奥さんは兵庫県から愛知県まで来ましたが、衣服などを差し入れるだけで、実際に会って話をすることはできませんでした。Aさんには子どももいたので、長時間の身柄拘束が続くと子どもにも影響が出かねません。
そのため、早期に身柄開放が必要でしたので、Aさんが起訴をされたその日に保釈の申し立てをし、裁判官に翌日の午後一番で面談を求めました。保釈を申し立てた以上はなるべく早期に申し立ての審査がされなければならないのですが、裁判所は検察庁に意見を聞いてからでなければ決定を出せないので、すぐに決定をもらうということはできません。Aさんの場合は翌日面談前に保釈許可が下おりたので、保釈金を納付して身柄を解放されました。
保釈申し立てをして身柄を解放できると、依頼者から大変感謝されます。また、弁護人としても充実感があります。Aさんの例は犯罪行為を認めていた事案だったので、保釈は比較的容易に認められました。ただ、本来であれば、捜査が完了し、起訴をされた段階では検察官と被告人は対等の関係に立たなければなりません。対等の関係で裁判を行うことでより真実に近づいた判断をすることができます。捜査機関が被告人の身柄を抑えている状況では対等とは言えません。ただ、現実では事実関係を争う否認事件では保釈がなかなか認めらません。早期に身柄を解放されたいので、やってもいない犯罪を認めて保釈を求めることもあります。そのため、被告人の身柄を抑えるのを原則とする現在の刑事裁判のあり方は改められなければなりません。
裁判員裁判の流れ
今回は、弁護人として体験した裁判員裁判事件を元に、裁判員裁判がどのように行われるのかをお話ししたいと思います。
これまでの刑事裁判との違い
裁判員裁判では、裁判を行う日(公判日)に間隔を置かず、連日公判を行うという形に変わり、集中して審理を行うようになりました。事前に何が争点なのか、証拠として何を調べるのかを準備する形になりました。 私が担当した事件では、裁判所に鑑定を求めていましたので、裁判では専門家に鑑定した内容について証言をしてもらうことがありました。
裁判の流れ
最初に、裁判員を選任します。毎年、裁判員候補者名簿が作成され、この中から事件ごとに呼び出しがなされます。選任手続では、事件関係者でないか、辞退希望があるかを聞かれます。検察官や弁護人は4人まで候補者を拒否できますが、裁判員に対して質問ができるわけではないので、誰を拒否するかの判断は非常に難しいです。
裁判員選任が終わると、裁判が始まります。選任された日の午後から裁判が始まる場合もありますし、選任された日の何日か後に始まる場合もあります。
公判で具体的に何を取り調べるのかは事前の手続で決まっていますが、裁判員は裁判官と一緒になって、当事者の言い分を聞き、証拠の取調を行います。証拠の取調といっても読み上げられた書類の内容を聞いたり、写真を目で見たり、証人や被告人の話を聞くというものなので、決して特別な技能や経験が必要なわけではありません。裁判員の中には、検察官や弁護人が思ってもいなかった視点から証人や被告人に質問をして、感心することもあります。
評議、評決
公判が終わると、裁判員は裁判官と一緒に、犯罪を犯しているのか、犯している場合にそれに対してどういう刑罰を科すのが妥当かを議論します(評議、評決)。
裁判員裁判開始後、これまで簡単に認められていた覚せい剤輸入事件での、覚せい剤であることの認識があったかという点で、簡単には故意を認めないという事案も増えてきました。裁判官が今まで常識と考えていたことをチェックされているといえます。裁判員裁判制度は様々な意見がありますが、被告人の権利保証という観点から一定の前進があったのも事実です。今後は、より制度を良くしていく取組が必要だと思います。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税込)
弁護士費用について、事件ごとの具体例を説明します。ただし、これらは、あくまで標準的な基準によるものですので、具体的な弁護士費用は、事案の複雑さや予想される労力など、個別の事案に応じて決められます。
報酬基準
刑事事件
着手金
| 事案簡明な事件 | 22万円〜55万円 |
|---|---|
| それ以外の事件 (否認事件、事件多数、 専門的知識を要する事件、 裁判員裁判対象事件など) |
33万円以上 |
報酬金
| 事案簡明な事件 | 22万円から55万円 |
|---|---|
| それ以外の事件 (否認事件や事件多数、 専門的知識を要する事件、 裁判員裁判対象事件など) |
33万円以上 |
- 事案により初めに預り金をお願いする場合がございます。
- 事案簡明な事件の場合、不起訴(検察官が起訴しなかった場合)になったり、刑の執行猶予、無罪判決或いは刑の減軽を受けることができた場合に上記の報酬金をいただきます。
- 否認事件や専門的知識を要する事件の場合、刑の執行猶予、無罪判決或いは刑の減軽を受けることができた場合に上記の報酬金をいただきます。
- 一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。




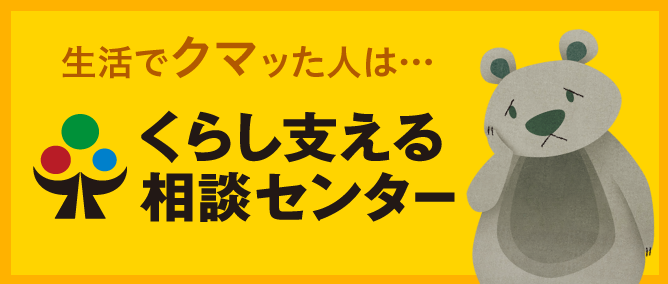



















逮捕された場合、起訴されるまでの捜査段階は最長で23日間であり、その段階で起訴するかどうかが決まってしまいます。早急に弁護人を依頼して活動することで、有利な処分、判決につながっていきます。