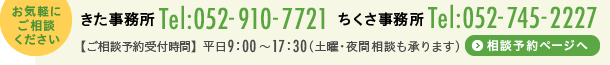駒場時代の思い出2 豆電球No.104
2009年12月25日
駒場時代の思い出2
生活は、楽ではなかった。
アルバイトは、家庭教師や塾の教師をしていた。週2回、2時間教えるだけで2万3000円から2万5000円程度のバイト料が貰えた。学生課の掲示板には、そうした家庭教師の募集カードが所狭しと張り出されていたので、そこから選んで自分で電話することになる。封筒に入ったバイト料を受け取るときも嬉しかったが、ピアノが置いてあるような中流以上の上品な家庭の子弟に勉強を教えるというのが、少し気恥ずかしいようなところがあった。教えていた子供より、勉強が終わった後、子供のお母さんがおいしい夕食を出してくれたのが嬉しかった。朝から晩まで針仕事をしていた母とは違う雰囲気の女性ばかりだった。
父母は、洋服仕立屋をやっていたが、紳士服の注文が激減して父親は仕立屋をやめて、近くの町工場に働くようになった。その厳しい生活の中で東京に仕送りを続けてくれた。授業料は、年間7万2000円、あるいは9万6000円程度であったという記憶であるが、私は父母の所得が低かったため、授業料免除の申請をして認められていた。
6た。話し合いで、テーマと書籍を選び、時々集まって感想を出し合うという程度のものだった。入学後も適当に本は読んでいた。高校3年の時から文学への愛好が芽生えていたので、近代文学や詩集等を読んでいたと思う。友人から勧められて、高橋和己とか柴田翔といった作者のものも読んだ、いずれも、60年代から70年代の安保闘争や学園紛争の後の若者の挫折感のようなものを反映していた。中身は覚えていないが。虚無的というか無力感のようなものを文学的に表現していたと思う。読書会に入ったのは、こうした自分に飽き足らなかったからだろう。
読書会で取り上げた本は、覚えていないものも多いが、「歴史の進歩とは何か」(陸井三郎)等の新書ものもあったか、ルポルタージュが多かった。本田勝一のベトナム戦争を描いた「殺す側の論理と殺される側の論理」、小田実の「何でも見てやろう」、労働現場の荒廃と搾取を描いた斎藤茂雄の「わが亡き後に洪水は来たれ」といったものだ。
読書会には、先輩が指導に入っていた。夏には、豊橋の伊良湖岬で合宿もしたりした。
読書会には、共通の目標が共有されていたような気がする。それは、学生は社会の現実を知らないという漠然とした自己認識であり、その反面として、社会を知らなければならないという志向だった。あるいは、東大闘争の名残の影響もあったかもしれない。当時の東大の中で行われていた論争に、東大解体論というものがあった。東大は帝国主義の手先であり、支配層を生み出すためのものだから解体すべきだという議論が、一部の学生、セクトから出されていて、駒場キャンパスには、いつも東大解体論を言い立てる立て看板があった。それ自体は間違った主張だと思うが、ただ、当時の学生は(少なくとも私の周囲では)、このままエリート街道を走って良いのだろうか、という負い目というような気持ちを持つ学生が少なくなかった。
また、駒場には良き教養主義というものがあった。専門の勉強は3年生からでよい、まずは幅広い教養を身につけるべきだ、という風潮である。今では、大学一年生から司法試験の勉強を始める東大生が少なくないというが、何となく寂しい気がする。
一年生の夏休みは、一か月まるまる実家の近くの工場でアルバイトした。乳酸飲料を作る工場が近くにあったので、そこで働いた。読書会で得た問題意識もあって、肉体労働の現場に行きたいという気持ちもあったと思う。