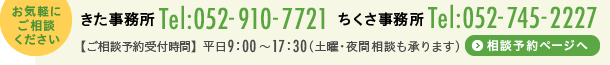裁判員制度と量刑1−「重罰化論」の盲点 豆電球No.98
2009年10月29日
裁判員制度と量刑1−「重罰化論」の盲点
裁判員制度のもとで、各地で裁判員が審理に参加する刑事裁判が始まった。メディアでも大きく報道され、裁判員を務めた市民が記者会見を行う場面も時々放映されているようだ。名古屋でも、先日、初めての裁判員裁判が行われたが、その前後は裁判所の庁舎の内外は傍聴券を求める人等で混雑していた。
刑事裁判に対して、これほど多くの市民から感心が寄せられ、茶の間の話題に上る時代は(戦前に陪審制が導入された時代は知らない)、初めてではないだろか。
これを機会に、是非、刑事裁判が国民にとって身近で信頼できる存在になってほしいと思う。
知られているように刑事事件の多くは、自白事件、すなわち被告人が犯罪事実を認めている事件が大半である。これまで報じられた裁判員裁判も、自白事件が多く、この場合、量刑が争点となる。報道でも、裁判員の参加により量刑判断にどのような影響があるのか、という視点からの報道が多いようだ。本稿では、この問題について少し考えてみたい。
メディア報道では、裁判員の方が量刑が厳しいとか、判決が検察官の求刑に張り付く傾向がある(求刑に近い判決となりやすい)といった指摘も出ている。
重罰化という傾向は、弁護人としての職務を遂行することを職責とする弁護士としては、危惧すべき傾向であり、弁護活動の改善と向上をはかったり、弁護活動を組織化していく等の対処が必要となる。悲惨な犯罪被害を前にして、被告人の有利な情状事実として指摘される事実は、どうしてもインパクトが弱く、裁判官や裁判員に訴える力が乏しい傾向にある。これを工夫することは、刑事裁判の弁護人を務めようとする弁護士として当然の課題である。
ここで述べたいのは、そうしたことではなく、量刑に関するこうした重罰化と言われる動向を国民としてどう考えるかということである。未だ事件数が少なく、裁判員制度が量刑に与える影響を論じるのは、いささか早すぎるかもしれないが、若干の感想を述べてみたい。
世上、人権派と呼ばれる向きから、この傾向について、重罰化は、「感情に流されやすい大衆の参加」「法廷重視による劇場型の裁判」としての裁判員制度の弊害であるかのような指摘がなされている。
最近の刑事裁判の量刑判断、特に生命に対する犯罪、強姦、酒気帯び運転等の悪質無謀運転による死亡事故等について、量刑判断が厳しくなっていることは事実である。しか、これは、これは裁判員制度導入前から生じていた傾向であり、犯罪被害者の権利の尊重が主張され、被害者の意見陳述等が刑事裁判で認められるようになったことが大きく影響している。
私が、重罰化を懸念する意見を聞いていて気になるのは、これまでの官僚司法に対する批判的見地が全く欠落していることである。あたかも、被害者の意見陳述等が導入される前の旧い刑事裁判こそが良かったのだという郷愁のようなものすら感じさせる意見もあるようだ。
私は、裁判員制度を含む司法制度改革を考える際、官僚司法の打破というものを一つの基本的視座としている。
以前にも書いたことであるが、かつての刑事裁判は、犯罪被害者に対して極めて不十分な顧慮しか払っていなかったこと、その結果、犯罪被害の実態が刑事裁判に十分反映されていなかったという傾向があったことは、否定できない。そして、その責任は、公訴権を独占し、被害者の権利に配慮しつつ適切な訴訟遂行を行うべき検察官の怠慢にあると考えている。
人間の生命が失われる事件ー殺人事件や酒酔い運転による死亡事故等を考えてみよう。法規範は、どうしても、個別的な事実を一般化し抽象化してとらえる傾向を生む。そこでは、「人間の死」というものがどうしても抽象化される。犯罪の成立要件を認定するためには、「死亡」という事実が認定されれば足りる。殺害された、あるいは事故死した被害者がどのような死に方を余儀なくされたのか、死に至らしめられた時の苦痛、恐怖、絶望、遺族がどのような言語に絶する苦痛を受けているのかという事情は、犯罪成立要件とは直接の関わりはない付随的事情となりがちである。また、毎日、刑事事件ばかりをやっている検事は、どうしてもマンネリに陥る。司法修習生は、検事になった時は、「被害者とともに泣く検事になりたい」と思う。しかし、年数がたつにつれ、どうしても犯罪事件処理と公判活動がルーティーンワーク化したり、初心を忘れがちになる。それは、個々の検察官の資質とか能力の問題ではなく、司法官によって訴追と審判という機能が独占されてきたという官僚的な刑事裁判システムがもたらす弊害である。
私は、弁護士として刑事事件にも一定数取り組んできたが、なぜ、検察官が情状立証のために被害者や遺族の証人尋問を請求しないのか、疑問を抱き続けてきた。
一般の読者には信じられないかもしれないが、10年くらい前は、飲酒運転の死亡事故ですら、遺族の証人尋問すら行われることは稀であり、情状立証について証人尋問が行われるのは弁護側申請の証人(被告人の妻であったり、勤務先であったりする)のみであり、検察側の立証は供述調書の取り調べのみ(朗読もなく、要旨の説明もさらっとしたものであった)、というのが通例であったと思う。当時は、飲酒運転による死亡事故でも執行猶予判決がついていた。そして、裁判官も、このような傾向を是正しようとは考えていなかったのである(被告人の権利と利益を擁護すべき弁護人側としては、語弊を恐れず言えば「ありがたい」時代ではあった)。
犯罪被害者の権利が主張されるようになったのは、根本的には、このような官僚的な刑事裁判のあり方に対する批判があることをしっかり見なければならない。これを忘れて、厳罰化は裁判員制度のせいだとか、裁判が国民感情に流されているといって問題視するだけでは、その批判の中に一片の道理が含まれているとしても、十分な説得力を持たないのである。