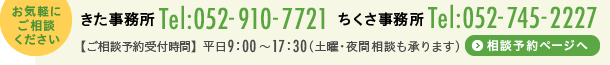続「千の風になって」 豆電球No.43
2007年12月28日
続「千の風になって」
今年2007年も、あと3日を残すのみとなった。
「千の風になって」については、豆電球№23で感想めいたことを書いたが、年末恒例の歌謡番組を見てみると、今でも「千の風になって」がロングヒットを続けている。この歌は、いま、どうして日本人の心を、私たちの心を、こうまで強く引きつける力を持つのだろうか。
先日、高校3年生の次女の勉強机を覗いてみると、現代国語の演習問題が置かれており、何げなくそれを読んでみると、死生観に関する一文(書籍からの抜粋 であろう)をテーマとした出題である。その内容が実に興味深いものであり、「千の風になって」の意味を考える上で貴重な示唆を与えてくれるものであった。 まさにわが意を得たりというか、自分の言いたいことを、理論的に整理してくれているという感覚を受けた。
著者は、宇都宮輝夫という方であり、出題論文のタイトルは「死と宗教」というものである(アマゾンで検索してみたが、そのタイトルの本は見あたらなかった。どなたかご存じの方がおられたら、出典を教えていただきたい)。
以下、いささか長くなるが、要旨を紹介してみたい(一部、強調点等に括弧をつけたりした部分がある)。
「何ゆえに死者の完全消滅を説く宗教伝統は人類の宗教史の中で例外的で、ほとんどの宗教が何らかの来世感を有しているのであろうか。なにゆえに死者の存 続がほとんどの社会で説かれているのか」と問いかけた著者は、「答えは、単純である。死者は決して消滅しないからである」と答える。
著者は、「現在の社会は、すべて過去の遺産であり、過去が沈殿しており、過去によって規定されている」「そもそも、『故人』とか『死んでいる人』という 表現自体が奇妙である。死んだ人はもう存在せず、無なのであるから。ということは、こうした表現は、死んだ人が今も『いる』ことを指し示している」「先行 者は生物学的にはもちろん存在しないが、社会的には実在する」「先行者は、今のわれわれに依然として作用を及ぼし、われわれの現在を規定しているからであ る」「死者が単なる思い出の中に生きている」のとはわけが違い、死者は依然として働きかけ、作用を及ぼし続ける実在である」という。
著者は、「人間の本質は社会性である」とした上で(マルクスも「人間は社会関係の総体である」と言っている)、「それは人間が同時代者に相互依存してい るという意味だけではなく、幾世代にもわたる社会の存続に依存しているという意味でもある」「換言すれば、生きるとは社会の中に生きることであり、それは 死んだ人間達が自分たちのために残し、与えていってくれたものの中で生きることなのである」と言う。
その上で、著者は、「以上のような過去から現在へというベクトル」は、「現在から未来へという方向とパラレルである」と述べ、次のように語る。
「人間は自分が死んだあともたぶん生きている人と社会的な相互作用を行う。ときにはまだ生まれていない人を念頭に置いた行為すら行う」
「人間は死によって事故の存在が虚無と化し、意味を失うとは考えずに、死を越えてなお自分と結びついた何かが存続すると考え、それに働きかける」
「千の風になって」が多くの人々の心に共感を及ぼすのは、その歌詞が、死の意味をごまかしたり、慰めたりするものだからではなく、このような人間の社会的 存在としての本質に根ざした死生観を反映しているからであると私は思うのである。私が死んだ後に生きているであろう人々、未だ生まれていない人々のために も、人類社会の合理的な進化のために、一日一日、自分の生命活動を重ねて、次の世代に道を譲るその時まで、歩んでいきたいと思う。
朝日新聞の加藤周一の今年最後の「夕陽妄語(12月19日)」は、2007年を振り返って、核兵器全面禁止、地球温暖化の緩和と阻止、という人類の死活 に関わる問題が重大な分岐点に立っていることを述べた上で、「私のいのちは、他のすべてのひとごとと同じように、あの遠い空を吹き渡っている…」と結ん だ。
2008年が皆様にとって幸多き年でありますように。