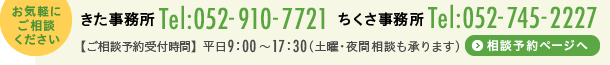続々「千の風になって」ー松井孝典を読みながら 豆電球No.57
2008年5月29日
続々「千の風になって」ー松井孝典を読みながら
宇宙物理学者の松井孝典は、以前に読んだ「宇宙史」に感動し、時々 チェックしている研究者だ。マスコミにも登場し「日本一受けたい授業」の一つに 選ばれたりしている。その近著、「宇宙生命、そして『人間圏』」は、人間とは何か、生と死などを考える上で学ぶところが多かった。「千の風に乗って」と松 井孝典の宇宙論というのは、意外な取り合わせと思われるかもしれないが、そこにミソがある。
松井教授は、宇宙、地球、生命の歴史をわかり やすく論じてくれる学者だが、98年にガンの手術を受け、入院生活を送り、「手術前夜から現在に至るまで、 自分にとって人生とは何か、我とは何か、人間とは何か、自分の心を観察しながら、あれこれと考え続けてきた」という。その「考え続けた」思索の後が、この 著作である。
松井は、「これまでの歴史学のように、『人間と自然』といった二元論的対立概念で規定された歴史では、我々が何者かさえ理解することはできない」と言 う。そして、「現代という時代の特徴は、我々の存在が、宇宙から見える、という点にある。我々は、現在という時代にはじめて、宇宙から地球や我々を俯瞰で きる視点を獲得した」と言っている。
松井は、江戸自体のようなフロー型資源(太陽エネルギーやそれによって育つ植物資源等)ではなく、石油や鉱物関連資源などのストック型資源を食いつぶし ながら生き続ける現代文明を批判し、それに対置する形で、「レンタルの思想」というものを提唱しているのだが、その中で、人間の命について次のような含蓄 に富んだ発言をしている。
「そもそも人間の存在そのものが『地球システム』からの『レンタル』だ。人間の肉体はつきつめていえば炭素で構成されている。しかし、死んで灰になれば その灰もまた炭素であり、その灰を地上にばらまけば、それは地球システムに戻ることになる。その滞留期間が人生というものだ」
人間は、地球から炭素を一時的にレンタルして「生きている」のであり、やがては「死んで」炭素として地球システムに戻り、そうして人間圏は「生きてい く」といいたいのであろう(松井によれば、人間の消費するエネルギーは、象一頭分に匹敵するらしい。食べものだけでなく、衣服や住宅その他の消費物資が巨 大なエネルギーを消費しているのである)。
近代主義の影響下に生きてきた私たちは、どうしても、「個」として、自然と対立するものとして、人間を、生と死を、捉えてきた。しかし、それでは、不十分ではないだろうか。
そもそも人間とは、何なのか、最近の諸科学の総括の上に立って、大きく俯瞰する視点を獲得した上で、もう一度考えなおす必要があると思う。
松井は、近代哲学の祖とも言うべきデカルトの箴言「我思う ゆえにわれあり」について、次のように述べる(私も豆電球№23で同じデカルトの言葉に触れた)。
「ここで思い出すのは、人間の定義として良く引用されるデカルトの『我思う故に我あり』という言葉である。我とは何なのかを考えている我は確実にいる、それが私の存在証明だといったいみなのだが、果たしてこの言葉は正しいと言えるのだろうか。
私に言わせれば、前述のように生身の知性を持つ人間は、その成長の過程で外界のあらゆるものとの間で相互作用を行うことで、はじめて我という概念を形成できる。外界と隔絶したなかで、我という概念だけが形成され、自分だけが悩んだり考えたり出来ないのは明らかである」
「『思う』という脳の機能から考えてみても、その概念が形成されるのは、他との関係を通じて脳の中にその情報が蓄積されるからである。外界と無関係に『思う』ことが出来る存在があるとすれば、それは『神』にほかならない」
こうして考えてくると、人間という存在は、不断に生成、変化、消滅を繰り返す宇宙の運動の一部であり、宇宙から離れた自己なるものは存在せず、地球から 炭素を一時的にレンタルされ、様々な物質系との相互関係を結びながら、ほんの一瞬の時空を過ぎ去るようなものではないだろうか。
このような人間の生命に関する巨視的な捉え方は、「千の風になって」に流れる死生観と通じるところがあるように思うのである。
な お、詳しく述べることはできないが、松井氏の世界観は、まさに弁証法的な世界観であり、唯物論的な世界観である。マルクスやエンゲルスが生きていた時 代には解明されていなかった地球や宇宙、生命に関する最先端の知識に裏打ちされながら、世界の統一性を物質生に求めるとともに、世界を不断に生成、発展、 消滅する過程として把握し、あるいは相互の連関の中で捉える立場である。
この点は、改めて述べてみたいと思っている。