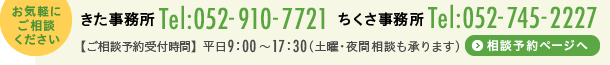読書のしおり(14)『永遠の0』百田尚樹vol.2
2014年12月18日
読書のしおり14
(13の続き)
私も百田さんも戦争を体験していない。戦争の本当の悲惨さを知らない世代である。
特攻に行かなければ愛する人を守れない、戦争に行かなければ愛する人を守れないのか?戦争に行けば愛する人を守れるのか?今の若者は利己主義か?という作者の問いかけについて疑問が頭からはなれない。戦争下であっても人間性を失わなかった宮部に生き残ってほしいと感情移入しながらも、この本は戦争を美化していないか?心が落ち着かない。
私も百田さんも1950年代生まれ。1960年代から1970年代に教育を受けた同じ世代である。しかし、考え方は違うようだ。
私が子供のころは、まわりの大人はみな戦争体験者であった。戦争に行った人、行かなくても学徒動員で勉強せず、工場で仕事をしたり、運動場を畑にしたり、空襲や原爆(広島県で育ったので)を受けた人が先生、親、祖父母、親戚の人たちであった。町に行けば、戦争で手足を失った傷痍軍人が白い着物をきて物乞いをしていた。庭には防空壕の跡も残っていた。
戦争体験を聞くのが中学校の毎夏休みの宿題だった。その中で強烈なのが祖母の話だ。祖父母は北九州に住み、八幡製鉄所の石炭を小船で運ぶことが生業であった。陸から見る夜間の八幡製鉄所の焼夷弾はきれいだったが、自分達が船に乗っていた時に焼夷弾が雨のようにふってきた翌朝の光景は、祖母にとっては忘れることができないものであったようだ。海上は、船の破片である木くずと死体で埋め尽くされ、それを棒で寄せながらでしか自分の船を動かせなかった。周りには、自分の船の他にわずかの船が残っているだけだったという。
もう一つの祖母の記憶は、機関銃照射である。低空飛行で米兵パイロットの顔が見える近さで追いかけられた。パイロットは笑っていた。とっさに、道を歩いていた人たちは溝に飛び込んだ。通り過ぎたと思いほっとしたすぐあとに、その飛行機は戻ってきた。飛行機が通り過ぎた後、恐る恐る顔を上げると、自分の前を歩いていた女の人は、溝の中で背負っていた赤ちゃんごと死んでいた。腰が抜けてしばらくは動けなかったという。紙一重で生死が分かれた。
私の高校の時の夏休みの宿題は、中学校の頃の宿題のうえに、自分がこの時代に生きていたとしたらどうしたか、を考えるものであった。
私は祖母に聞いた。「どうして戦争に反対しなかったの?」。祖母の答えはいつも「気がついたら戦争になっていた」「反対することは非国民だったから、そんなことは考えもしなかった」。戦前は女性に選挙権は無かった。
高校三年間、同じ宿題が出た。その時の国語の先生は、被爆者だった。14歳の時だったそうだ。だから、私達に「流されるな。自分で考えろ。」と常に話していた。私がその頃生きていたとしたら何ができたのか、三年間考えたけれども、結論は出なかった。ただ、無関心でいることはいけない。無関心でいることは、賛成していることと同じだ。だから、世の中のことから目を離さないことが大事なのではないかと思ってきた。
昭和30年代から40年代、広島で教育を受けた人はみな、同じようなことを自然に思っているのではないかと思う。これが平和教育だと思う。しかし、一歳上の夫は、愛知県で生まれ育ったが、平和教育については私とはかなり違いがある。私が受けたものは、広島という特殊性が生んだ平和教育かもしれない。他にも小学校では、「原爆許すまじ」を歌い、ベトナム戦争や原爆、沖縄戦の写真集を見、原爆ドームや資料館を見学し、中学校では、「イムジン河」を歌い、その背景である朝鮮戦争を学んだ。
だから、百田さんの『永遠の0』『海賊になった男』などを読むと、どうしても諸手を挙げて「すごく良かったよ」などと言うことはできない。これを見て、読んで、戦争に、ゼロ戦に憧れる人が出てくるかもしれないと思うだけで、やりきれない。
「愛する人を守るため」に戦争に行ったとしても、戦争になれば「愛する人」はみんな死んでしまうのである。イラン、イラク、アフガニスタンを見れば、一般市民がたくさん死んでいる。戦地は、戦争に行った場所だけではない。今の戦争に「戦地」はない。自分の家、故郷、生活の場所すべてが「戦地」になるのである。
私は、戦争を美化するものについては、良い本だと評価されていても、どうしても受け入れることはできない。この本や映画を見て「良かった」と感動した人は、何に感動したのだろうか。愛する人を守るということなのか。しかし、戦争は人災である。
あの戦争で大きな犠牲を払って学んだことは、戦争で亡くなった人達を賛美することではなくて、二度と戦争を起こさない努力をすること、武力でなく、話し合いで解決するということだったのではないか。
2014/12/18 長谷川弘子