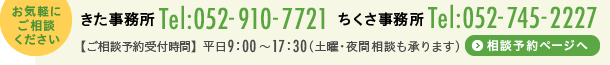「悼む人」 豆電球No.79
2009年4月3日
「悼む人」
何となく重そうなテーマを感じたので触手が伸びなかった天童荒太の「悼む人」を長尾事務局長の勧めで読んでみた。
主人公の静人は、交通事故、災害や犯罪等により不慮の死を遂げた人々の死亡現場を訪ね、そこで「悼む」。「悼む」とは何か。冥福を祈ることとも違うという。ただ、故人の記憶を記憶し、自分の胸(心))にしまい込む独特の行為である。
静人は、悼む行為を行う時、新聞記事やテレビ報道、知人や隣人等からの情報で死者について特定のイメージを形成し、それを胸にしまいこむのだが、静人が死者について尋ねる事柄は、次第に次の三つに収斂されていく。
死者は誰を愛したか。
死者は誰に愛されたか。
死者は何をして誰に感謝されたか。
この三つで有れば、どんな死者でも、例え赤ん坊であっても、例え犯罪を犯した人であっても、共通して、その存在を確かめ、悼むことができる。静人は、放浪生活をしながら、死亡現場を訪ね、この三つを確かめ、悼むという生活を送り続ける。
これがストーリーの中心軸であり、その周辺に、犯罪事件をネタに週刊紙に売れる記事を書くことを生業にしており、時には事実をねつ造したり装飾することも厭わないフリーライター、する末期ガンに冒された実母順子の病床での生活と静人との交流、夫の暴力が発端となって夫を殺害した女性等が、それぞれ死と生について自問自答しながら、中心軸である「悼む人」静人の魂の遍歴に彩りを添え、その意味を引き出す役割を果たしている。
この書は、私の読解力を越えており、静人や周辺の人物の語り口も哲学的で観念的なものであり、作品を十分理解できたとはとても言えない。しかし、訴えたいメッセージは、作品の中で比較的明瞭に示されている。
静人の母が、癌で死ぬ直前、父が自死した四国の海辺を訪れた際、静人の「悼み」について次のように述懐する場面がある。
「どの死は覚えておくべきで、どの死は忘れられても仕方がないのだろう。静人、あなたが言いたかったことはそれだったの?誰かの死を忘れても仕方がないものにしてしまうなら、結局は、あらゆる人の死が忘れられても仕方がないことになつてしまうんじゃないか」
文藝春秋の特設サイトの中での松田哲夫氏との対談の中で、作者の天童氏自信、次のように作品のモチーフを語っている。
「いわゆるニュース価値のないありふれた死でさえ、同等に大切に扱う心がない限りは、生きている人を差別したり、虐げたりすることもなくならないのではないかと感じたんです。そして、どんな死者であれ、誰かを愛し、誰かに愛された経験をそれぞれ抱えていて、深く悼まれるべき人物なんだという考えが日常化すれば、どんな人の命も簡単に奪ってよいものではないというわきまえが、感情レベルで人々の心に浸透していくのではないか」
メディアが発達し、報道の中で事故死や災害死、殺人事件がありふれた事件報道として「消費」されていく現代社会にあって、あらためて心に銘じるべきテーマがここにあることは間違いない。
このような作品がベストセラーになる現代というのは、どういう事態なのだろうか。「なぜ人を殺害してはいけないの」「なぜ、自殺してはいけないの」という疑問を持つ若者も少なくないと聞く。倫理とは、歴史を越えた普遍的なものであり、人間なら当然に持ち合わせているはずであるという理解もあるが、倫理も歴史の中で形成されるべき文化である。「どんな人間であっても簡単に奪って良いものではない」という倫理と文化が維持され、より深く根付いていくためには、芸術家の営為を含めた人間社会の意識的な努力が求められる時代になっている、ということかもしれない。