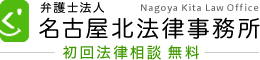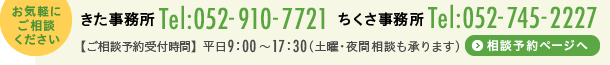刑事再審制度の問題点
2025年1月15日
昨年9月26日に、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖さんに対し、再審無罪判決が言い渡されました。この件は、1966年6月30日未明に発生した一家4名の殺害事件で、袴田巌さんが逮捕、起訴され死刑判決が確定した事件です。袴田さんは長時間の強制的な取調べにより一旦は自白したものの、公判に至って自白を翻し、以後一貫して無実を主張してきました。確定後も二度にわたる再審請求を行い、47年間もの拘束期間を経て、無罪判決が言い渡されたのです
この判決の注目点は、袴田さんを犯人と推認する有罪判決の根拠とされた重要な証拠には「三つのねつ造がある」と認定した点です。もともとこの事件は、一審の有罪判決でも自白調書の多くが任意性を欠く(自由な意思で述べられたものでない)とされており、捜査機関の捜査手法が問題視されていました。
日本の再審制度は、再審を開始するかどうかをまず判断し、再審開始が決まると、再度刑事裁判を開いて有罪か無罪かを判断します。この「袴田事件」は、2度の再審請求を経ていますが、その期間は約43年になります。また、再審開始後30年たって、約600点もの証拠が検察側から開示され、それらが判断に大きく影響を与えました。
「袴田事件」が非常に長い時間を要した原因は、現在の刑事訴訟では、再審における証拠開示の制度が定められていないこと、再審の審理をどのように進めるかという手続規定(ルール)が定められていないこと、再審を開始するという決定に対して、検察官が不服を申し立てることができることにあるといわれています。
裁判に関わる法曹も人間である以上、誤りとは無縁ではいられません。再審を開始したとしても、あらためて有罪か無罪かを判断すればよいだけです。当初の判決を揺るがしかねない証拠が見つかれば、なるべく広く再審を認めて、当初の判断が正しかったのかを検証する機会が与えられるべきでしょう。
弁護士 白川秀之(名古屋北法律事務所)
(「年金者きた」へ寄稿した原稿を転機しています)